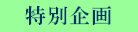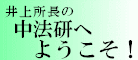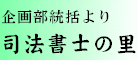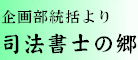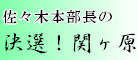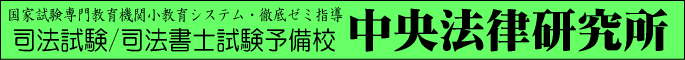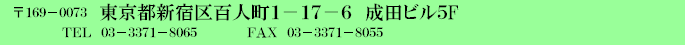第5回目の今週は、第25問について見ていきましょう。
[問題]
不動産の二重譲渡に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、理由付けが適切でないものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
教授
「AはBとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結し、甲土地をBに引き渡したが,、AからBへの所有権移転登記はまだされていない。Cは、そのような事実を知りつつ、Aから甲土地の贈与を受け、AからCへの所有権移転登記がされた。CがBに対して、所有権に基づいて甲土地の明渡しを請求した。」という事例を素材に、不動産の二重譲渡の場合の法律関係を勉強しましょう。
まず、BはCに対して自己の所有権取得を対抗することができますか。
学生ア
BはCに対して対抗することができます。その理由は、私は民法第177条の第三者の範囲として悪意者排除論を採るので、たとえBの売買代金債務の履行期が過ぎているとしても、この場合のCは第三者に当たらないからです。
教授
BはAC間の贈与を詐害行為として取り消すことができますか。
学生イ
AからCへの贈与によってAが無資力となったときは、Cが悪意であればBは贈与を取り消すことができます。その理由は、特定物債権も究極的には損害賠償債権に変わりうるものなので、債務者の一般財産により担保されなければならない点では、金銭債権と同様だからです。
教授
Aが無資力になりCが悪意であればBは詐害行為取消権を行使できるとした場合、Bは,詐害行為取消権を行使して、CからBへの所有権移転登記を請求することができますか。
学生ウ
請求することができます。その理由は、二重譲渡におけるCの悪意と詐害行為取消権における受益者であるCの悪意は同一のことなので、悪意者排除論を採るならば、特定物債権保全のために、CからBへの直接の所有権移転登記の請求を認めても不当な結果にはならないからです。
教授
BはCに対して、不法行為に基づく損害賠償として甲土地の時価相当額の支払を請求することができますか。
学生エ
請求することはできません。その理由は,このような場合に債権侵害による不法行為が成立するためには、AとCが通謀していたり、Cに害意があることが必要ですが、これは、結局、Cが背信的悪意者である場合にほかならないので、背信的悪意者排除論を採らない限り、不法行為の成立は認められないからです。
教授
Bは留置権の抗弁をCに対して主張することができますか。
学生オ
Bは留置権を根拠に甲土地の明渡しを拒むことはできません。その理由は、BはAに対して売買契約の履行不能に基づく損害賠償請求権を有していますが、この損害賠償請求権は、甲土地自体を目的とする債権が変容したものであって、甲土地に関して生じた債権とはいえないからです。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ エ 5.ウ オ
|
[検討]
法務省のHPによれば、本問の正解は
“4”となっており、「適切でない」のが
“肢ウ”と
“肢エ”ということになります。
そこで、「適切」と思われる
“肢イ”と
“肢オ”から見てみましょう。
“肢イ”では、
詐害行為取消権において、特定物債権が被保全債権となるか?が聞かれています。
この点、特定物債権も、究極において金銭債権に変じ得るものであるから被保全債権となり得ます(最大判昭36年7月19日)。
そのため、Aに対して甲土地の所有権移転登記請求権を有しているBは、債務者であるAが無資力となった場合には、AのCに対する贈与を詐害行為として取り消すことができます。
よって、本肢は“適切”といえます。
このことは、過去問昭和51年第51問肢(2)でも聞かれており、
『押さえるべき肢』といえます。
“肢オ”では、
Bの債務不履行に基づく損害賠償請求権が「その物に関して生じた債権」(物と債権の牽連性)といえるか?が聞かれています。
この点、Bの甲土地の所有権移転登記請求権は、“物自体を目的とする債権”ですが、この場合、権利の内容をなす行為をすればよいので、物を留置して弁済を強制する関係にはありません。
そして、このことは、物自体を目的とする債権が、損害賠償債権に変わっても同様です(最判昭43年11月21日参照)。
よって、Bの債務不履行に基づく損害賠償請求権は「その物に関して生じた債権」とはいえず、本肢は
“適切”といえます。
同じことは、過去問昭和58年第59問肢3・平成11年第24問・平成15年第23問肢イでも聞かれており、これもまた
『押さえるべき肢』といえます。
この時点で選択肢を検討すると、
消去法により、選択肢4が正解とわかります。
ちなみに、他の肢も見てみますと、
“肢ア”では、177条の“悪意者排除論”からの帰結が聞かれています。
“悪意者排除論”によれば、第一譲受人がいることを知っている者は、177条の「第三者」にあたらないことになります。
そして、第二譲受人Cは、第一譲受人がいることを知っているので「第三者」にはあたらないことになります。
このことは、Bが代金債務を履行したか否かによって異なりません。よって、本肢は
“適切”といえます。
この肢は、現場でのあてはめさえできればよいという肢です。
また、
“肢ウ”では、詐害行為取消権の効果に関連して、
① 二重譲渡における第二譲受人の『悪意』と詐害行為取消権の要件における受益者の『悪意』が同一であること、
② ①を前提として、悪意者排除論を採るとき、取消権を行使した債権者への直接の所有権移転登記の請求を認めても不当な結果にはならないこと、の二点から
「直接の所有権移転登記請求を認める」という結論が導けるか?が聞かれています。
確かに、
悪意者排除論を採った場合、Cが『悪意』であれば、第一譲受人であるBは、Cに対して所有権に基づく請求が可能になりますので、詐害行為取消で直接の移転登記請求を認めたところで格別不利益は生じないともいえます。
しかし、二重譲渡における第二譲受人の『悪意』が“第一譲受人への実体上の物権変動があったことを知っていること”であるのに対し、詐害行為取消権における受益者の『悪意』は、“債権者を害すべき事実を知っていること”であるから、両者は同一とはいえません。
従って、①が誤っている以上、本肢は“適切でないもの”といえます。
この肢は、現場で読んでみて、
「なんか①怪しくねぇ?」と気付いて保留できればよい肢でしょう。
“肢エ”では、
① 債権侵害による不法行為が成立するには、通謀や害意があることが必要である。
② 通謀や害意がある場合、背信的悪意者といえる。
③ ②の場合には、背信的悪意者排除論を採らない限り、不法行為の成立は認められないの三つが適切といえるか?が聞かれています。
①について、本問のような
“二重譲渡”の場合は、“給付侵害”にあたり、
不法行為の成立要件として通謀や害意があることが必要とされています。
なので、この部分は適切といえます。
次に、②についてみると、背信的悪意者とは、
“登記欠けつの主張が自己の行為に矛盾して信義則に反する場合”や
“第二譲受人に反倫理的な意図動機があって、信義則に反する場合”などをいいますが、通謀や害意がある場合は、この後者にあたると考えられます。
なので、この部分も適切といえるでしょう。
最後に、③ですが、
“背信的悪意者排除論を採らない限り、不法行為の成立は認められない”ということは、
“背信的悪意者排除論を採れば、不法行為が成立する”といえます。
そして、背信的悪意者排除論を採り、通謀や害意がある場合に“背信的悪意者”になるとすると、通謀や害意がある第二譲受人は「第三者」にはあたらないことになります。とすると、この者に対して、第一譲受人は登記なくして所有権を対抗できるので、権利の侵害は無く、不法行為は成立しないことになります。
このように考えれば、③は不適切ということになります。
以上から、本肢は
“適切でないもの”といえます。
[まとめ]
以上から、第25問における「関ヶ原」は、
“肢イ”と
“肢オ”といえます。
戻る