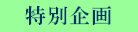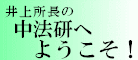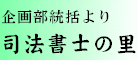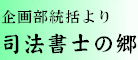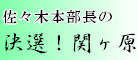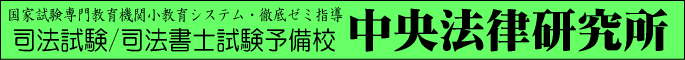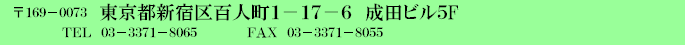第20回の今週は、第40問について見ていきましょう。
[問題]
相続財産に関する教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
| 教授 |
共同相続人の中に被相続人から婚姻のための贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして具体的相続分の算定を行います。では、この贈与を受けた共同相続人が相続開始後に相続の放棄をした場合も、この贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして具体的相続分の算定を行いますか。
|
学生ア |
その贈与を受けた共同相続人が相続放棄をしたときも、この贈与が推定相続人に対するものであることは変わりませんので、この贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして具体的相続分の算定を行います。
|
教授 |
被相続人が共同相続人ではない第三者Cに対し甲不動産を含む全部の財産の3分の1を遺贈する旨の遺言を残した場合、Cが甲不動産について共同相続人A及びBとの共有関係を解消するにはどのような手続によりますか。
|
学生イ |
Cは共同相続人ではないので、相続人間の遺産分割手続に参加することはできません。他方、遺産共有は物権法上の共有の性質を有しますので、この場合、Cは共有物の分割手続によってA及びBとの共有関係を解消します。
|
教授 |
相続開始時に被相続人の財産の中に金銭や売掛代金債権があった場合、共同相続人は、これらを遺産分割の対象とする必要がありますか。
|
学生ウ |
金銭は共同相続人間で遺産共有の関係になりますので、これを遺産分割の対象とする必要があります。しかし、可分債権は、相続開始と同時に、相続分に応じた分割債権として各共同相続人に帰属しますので、売掛代金債権については遺産分割の対象とする必要はありません。
|
教授 |
では、相続開始時に被相続人の財産の中にあった不動産を共同相続人全員が合意して売却した場合の代金債権は、遺産分割の対象とする必要がありますか。
|
学生エ |
共同相続人全員によって売却された不動産は、遺産分割の対象となる相続財産から逸出しますので、その売却代金債権も、共同相続人間で特別の合意をしない限り、遺産分割の対象とする必要はありません。
|
教授 |
被相続人から全部の財産を包括遺贈された共同相続人に対し遺留分権利者が減殺請求をした場合、この遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産の性質を有しますか。
|
学生オ |
特定遺贈の目的財産は遺産分割の対象となる相続財産から逸出しますので、特定遺贈の受遺者に対する減殺請求によって遺留分権利者に帰属する権利も、遺産分割の対象となる相続財産の性質を有しません。全部の財産の包括遺贈は、特定遺贈の集積と考えられますので、この場合も、遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産の性質を有しません。
|
1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ エ 5.ウ オ
|
[検討]
法務省のHPによれば、本問の正解は
“1”となっています。
本問の肢は、いずれも過去問での出題がありません。
しかも、相続という試験対策の手薄な分野に関する出題ですので、はっきり言ってしまえば、
「捨て問」でしょう。
ただ、それで終わってはこのコーナーの趣旨に反するので、以下、いつものように検討していくことにします。
まず、
“肢ウ”では、
“金銭や金銭債権が遺産分割の対象となるか?”が聞かれています。
この点、現金について、
判例は、相続人は、相続財産として現金を保管する他の共同相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることができないとしているので(最判平4年4月10日)、遺産分割の対象になります。
これに対し、金銭債権の場合、相続の開始によってその債権は共同相続人に共有的に帰属します。
そして、金銭債権は、可分な給付を目的とするため、
427条により、各共同相続人がそれぞれ等しい割合で権利を有することになります(最判昭29年4月8日参照)。
そのため、その金銭債権は、遺産分割の対象とはなりません。
以上から、本肢は、“正”といえます。
現金が、遺産分割において相続人間の公平を図る機能をもつことからすれば、現金が遺産分割の対象となることは判断できます。
また、可分な給付を目的とする債権が、相続開始と同時に各相続人に分割帰属することについては、基本的な教科書であるSシリーズⅤの142頁にも記載があることから、本肢は、
『押さえておきたい肢』といえます。
次に、
“肢エ”では、
“相続財産中の特定の財産を売却した代金債権は、遺産分割の対象となるか?”が聞かれています。
この点、遺産分割の対象となるのは、共有関係にある相続財産ですが、
特定の相続財産を売却した代金債権は、各相続人の持分に応じて分割取得され(最判昭54年2月22日)、共有となるわけではないので、遺産分割の対象とはなりません。
よって、本肢は、“正”となります。
相続人全員で処分した特定の相続財産の代金が各相続人に分割帰属する点については、基本的な教科書であるSシリーズⅤの142頁にも記載があるので、本肢も、
『押さえておきたい肢』といえます。
以上から、
“肢ウ”“肢エ”を含む選択肢「3」「4」「5」が切れます。
そして、残った選択肢「1」「2」を見ると、
“肢ア”が共通しているので、
“肢イ”と
“肢オ”について検討します。
“肢イ”では、前半部分で
“包括受遺者が遺産分割に参加できるか?”が、後半部分では
“包括受遺者が、特定の相続財産の共有関係を解消する方法”が、それぞれ聞かれています。
まず、包括受遺者も遺産分割の当事者となることから、本肢の前半部分は“誤”となります。
次に、後半部分については、
990条により、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものとされることから、包括受遺者が、特定の相続財産の共有関係を解消するには、遺産分割によることとなります。
Cは、被相続人から全財産の3分の1の遺贈を受けた者ですから、包括受遺者にあたります。
そのため、Cが、A及びBとの共有関係を解消するには、遺産分割手続によることとなります。
よって、本肢後半部分も、“誤”となります。
この肢の前半部分に関する知識は、基本的な教科書であるSシリーズⅤの190頁に記載のある基本的知識といえるので、本肢は、
『押さえるべき肢』といえます。
なお、後半部分については、共同相続人の一人から共有持分権を譲り受けた者が、共有関係を解消する方法として共有物分割の手続(256条・258条)によることと混同しないように注意する必要があります(実は、私がこの問題を最初に解いたときもこれと混同しました・・・)。
この時点で、選択肢「1」が正解となります。
ちなみに、残りの肢も検討すると、
“肢ア”では、
“特別受益を受けた相続人が相続放棄をした場合にも、その受益が「みなし相続財産」の算出にあたり加算されるか?”が聞かれています。
この点、“みなし相続財産”の算出に際しては、特別受益が加算されるので、特別受益者は“持戻義務”を負うことになります。
この“持戻義務”を負うのは、共同相続人に限られますが、
相続放棄した者は、相続開始時に遡って相続人でなかったことになる(939条)ので、“持戻義務”を負いません。
よって、本肢は、“誤”となります。
この知識は、Sシリーズにも記載がありません。
ただ、“特別受益の加算”が、共同相続人間の公平を図ることを趣旨としていることからすれば、相続放棄によって相続人でなくなった者は、被相続人の財産を承継しないので、共同相続人間の公平を考える必要はなく、その者に対する特別受益を「みなし相続財産」の算出にあたって加算する必要はないと考えられます。
とすれば、本肢も
『押さえておきたい肢』といえます。
“肢オ”では、
“包括受遺者に対する遺留分減殺請求により、遺留分権者に帰属することとなった権利は遺産分割の対象となるか?”が聞かれています。
この点、遺留分減殺請求権の性質が、形成権と解されていることから、本来遺留分権者に帰属すべき権利が、遺留分減殺請求によって、当然に遺留分権者に復帰することになります。
そして、特定遺贈の場合、目的物の権利は、相続開始とともに受遺者に帰属し、遺産分割の対象とはならないので、特定遺贈の受遺者に対して遺留分減殺請求権を行使して得られた権利も遺産分割の対象となりません。
また、包括遺贈の場合について、
判例は、遺産すべての包括遺贈に対して遺留分減殺請求権を行使した場合に、帰属する権利は遺産分割の対象とはならないとしています(最判平8年1月26日)。
以上から、本肢は、“正”となります。
この判例についてはSシリーズⅤの190頁に記載がありますが、遺留分減殺によって得られた権利が遺産分割の対象となるかについては記載がありません。
なので、本肢は、
『知らなくてもよい肢』といえるでしょう。
[まとめ]
本問は、難問の部類に入ると思います。試験当日にはできなくても仕方なかったといえます。
ただ、一度出題された以上は、この機会に押さえておくべきでしょう。
以上から、第40問における「関ヶ原」は、
“肢ウ”、
“肢エ”及び
“肢イ”といえます。
[最後に]
これまで、20回にわたりお付き合いいただき、ありがとうございました。
今回の企画が、来年の皆さんの合格にとって、お役に立てば幸いです。
そして、皆さんが合格された暁には、ぜひ、合格体験記などで
「中法研の“決選!関ヶ原”で合格しました」と書いていただきたく思っております。
皆さんの最終合格を、心から願っております。
戻る