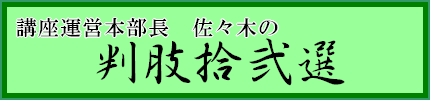
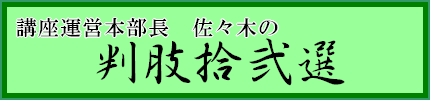
|
判例学習のポイントは、その“絞込み”にあると考えます。今回は、その切り口の一つとして、過去問での出題頻度で“絞込み”をかけてみようと思います。 平成元年から18年までの過去問をもとに、出題頻度を調査し、出題回数の多い判例を全12回に渡って紹介します。 このコーナーでは、《コメント》《事案》《判旨》の3項目を掲載します。
中法研の独断と偏見で加工しているので、「中法研と心中はまっぴら御免だ!」という方は、お手持ちの判例集で確認してください。 それでは、早速始めましょう! |
第1回 マクリーン事件(昭和53年10月4日 最高裁判決)
第2回 八幡製鉄事件(昭和45年6月24日 最高裁判決)
第3回 愛媛県玉串料訴訟(平成9年4月2日 最高裁判決)
第4回 特別区区長公選廃止事件(昭和38年3月27日 最高裁判決)
第5回 警察法改正無効事件(昭和37年3月7日 最高裁判決)
第6回 薬事法距離制限違憲判決(昭和50年4月30日 最高裁判決)
第7回 小売市場事件(昭和47年11月22日 最高裁判決)
第8回 博多駅テレビフィルム提出命令事件(昭和44年11月26日 最高裁決定)
第9回 川崎民商民商税務検査拒否事件(昭和47年11月22日 最高裁判決)
第10回 旭川学テ事件(昭和51年5月21日 最高裁判決)
第11回 三井美唄労組事件(昭和43年12月4日 最高裁判決)
第12回 共産党袴田事件(昭和63年12月20日 最高裁判決)

|
記念すべき第1回目は、“マクリーン事件” 言わずと知れた重要判例中の重要判例です。 平成6年第2問・平成11年第11問・平成18年第2問と3回も出題されています。 判旨も、ただ闇雲に読んでいたのではなかなか頭に入りにくいものです。 そこで、「何を言うための判断だったのか」を意識して読んでみるとよいでしょう。 マクリーン事件では、法務大臣の在留期間更新不許可処分の違法性が問題となりました。 《判旨》の(二)の部分で、法務大臣の判断が違法となるための要件を指摘した上で、(三)であてはめています。 有名な「外国人の政治活動の自由」のくだりは、 法務大臣の判断が『全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らか』かを判断する際になされたものです。 要するに、 『外国人にも政治活動の自由が保障されるけど、だからといって法務大臣の判断は拘束されないよ。だから法務大臣の判断に問題はないよ。』 ということなんですね(少し意訳しすぎですが…)。 この点を意識して《判旨》を読んでみてください。 |
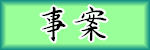
|
アメリカ人のロナルド・アラン・マクリーン氏が、 法務大臣の「在留期間更新不許可処分」の取消しを求めた事件 |
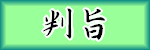
| (一) 憲法二二条一項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していない。 このことは、国際慣習法上、国家は、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される。 したがって、 憲法上、外国人は、わが国に入国する自由・在留の権利・引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものではない。 この憲法の趣旨を前提として、出入国管理令は、外国人に対し、一定の期間を限り、わが国への上陸を許すこととしているものであるから、上陸を許された外国人は、その在留期間が経過した場合には当然わが国から退去しなければならない。 もっとも、出入国管理令は、当該外国人が希望するときには在留期間の更新を申請することができるとし、その申請に対しては法務大臣が 「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができるものと定めている。 そして、その判断基準が特に定められていないことから、更新事由の有無の判断は法務大臣の広汎な裁量に委ねられている。 (二) 行政庁の処分は、法の認める裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に違法となる。 そして、出入国管理令二一条三項に基づく法務大臣の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断が違法となるのは、法務大臣の判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合である。 (三) 以上の見地に立って、被上告人の本件処分の適否について検討する。 上告人の在留期間更新申請に対する法務大臣の不許可処分は、上告人の在留期間中の無届転職と政治活動を理由としており、なかでも政治活動が重視されたものと解される。 思うに、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、 権 利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由に ついても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障 が及ぶ。 しかしながら、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないので、在留期間中になされた、憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。 在留中の外国人の行為が合憲合法な場合でも、法務大臣がその行為を当不当の面から日本国にとって好ましいものとはいえないと評価し、また、右行為から将 来当該外国人が日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者であると推認することは、右行為が上記のような意味において憲法の保障を受けるものであるか らといってなんら妨げられるものではない。 上告人の在留期間中のいわゆる政治活動は、その行動の態様などからみて直ちに憲法の保障が及ばない政治活動であるとはいえない。 しかしながら、上告人の右活動のなかには、わが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影響を及ぼすおそれがないとはいえないものも含まれており、 法 務大臣が、当時の内外の情勢にかんがみ、上告人の右活動を日本国にとって好ましいものではないと評価し、 また、上告人の右活動から同人を将来日本国の利益を害する行為を行うおそれがある者と認めて、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるも のとはいえないと判断したとしても、その事実の評価が明白に合理性を欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえない。 他に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったことをうかがわせるに足りる事情の存在が確定されていない本件においては、被上告人の本件処分を違法であると判断することはできないものといわなければならない。 |

|
さて、第2回目は、“八幡製鉄政治献金事件”。 これもまた、知らない人はいない重要判例です。 平成15年第5問・同第9問でズバリ聞かれており、それのみならず、平成5年第7問・平成8年14問では、前提知識として聞かれています。 本判決は、取締役の政治献金が旧商法266条第1項5号「法令又ハ定款ニ違反スル行為」といえるかが争われています。 ここでの主張は以下の3点です。
皆さんがよく目にするフレーズとして、『政党の憲法上の地位』の部分と『法人の政治活動の自由』の部分とがありますが、前者は①において政治献金が会社に期待・要請される行為であることをいうための事情であり、後者は②において政治献金が公序良俗に反しないことをいうための事情です。 この点に着目して判旨を読んでみてください。 |
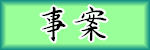
| 株主が、取締役のなした政治献金が「法令・定款」に違反するとして、取締役の責任(旧商法266条第1項)を追及した株主代表訴訟。 |
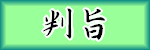
|
一 定款違反について 会社は定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するが、目的の範囲内の行為とは、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為をいう。 会社は、社会的実在として社会的作用を負担せざるを得ない以上、社会通念上、会社に対して期待・要請される行為を行うことができる。 そしてこの行為は、会社にとっても、企業体としての円滑な発展を図るうえで相当の価値と効果を認めることができるから、会社に対し期待・要請される行為もまた、間接的に、目的遂行のうえに必要なものであるといえる。 以上の理は、会社が政党に政治資金を寄附する場合においても同様である。 憲法は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないのであるが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。 そして同時に、政党は国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから、政党のあり方いかんは、国民としての重大な関心事でなければならない。 したがって、政党の健全な発展に協力することは、会社に対して期待されるところであり、政治資金の寄附もその一態様である。 会社の構成員が政治的信条を同じくするものでないとしても、会社による政治資金の寄附が、会社に対して期待・要請されるかぎりでなされる以上、会社にそのような政治資金の寄附をする能力がないとはいえない。 本件政治資金の寄附は、八幡製鉄株式会社の定款の目的の範囲内の行為である。 二 法令違反について(その1) 株式会社の政治資金の寄附が、国民の参政権を侵害するものとして憲法に反し、民法九〇条に反しないか。 確かに、憲法上の参政権は自然人たる国民にのみ認められたものであることは、所論のとおりである。 しかし、会社が、納税の義務を有する以上、納税者たる立場において、国や地方公共団体の施策に対し、意見の表明その他の行動に出たとしても、これを禁圧すべき理由はない。 のみならず、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。 政治資金の寄附もまさにその自由の一環である。 論旨は、会社が政党に寄附をすることは国民の参政権の侵犯であるとするが、政党への寄附は、事の性質上、国民個々の参政権の行使そのものに直接影響を及 ぼすものではないばかりでなく、政党の資金の一部が選挙人の買収にあてられることがあるにしても、それはたまたま生ずる病理的現象に過ぎず、しかも、かか る非違行為を抑制するための制度は厳として存在するのであって、いずれにしても政治資金の寄附が、選挙権の自由なる行使を直接に侵害するものとはなしがたい。 所論は大企業による巨額の寄附は金権政治の弊を産むべく、また、もし有力株主が外国人であるときは外国による政治干渉となる危険もあり、さらに豊富潤沢 な政治資金は政治の腐敗を醸成するというのであるが、その指摘するような弊害に対処する方途は、さしあたり、立法政策にまつべきことであって、憲法上は公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有するといわざるを得ず、これをもつて国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用のかぎりでない。 以上説示したとおり、株式会社の政治資金の寄附はわが憲法に反するものではなく、民法九〇条に違反するものではない。 三 法令違反について(その2) 取締役による本件政治資金の寄附は、商法二五四条ノ二に定める取締役の忠実義務に違反するか。 この点、取締役が、その職務上の地位を利用し、自己または第三者の利益のために、政治資金を寄附した場合に、忠実義務違反が認められる。 会社が政治資金の寄附をなしうる以上、取締役が会社の機関としてその衝にあたることは、特段の事情のないかぎり、取締役たる地位を利用した、私益追求の行為だとすることはできない。 い うまでもなく取締役が会社を代表して政治資金の寄附をなすにあたっては、その会社の規模、経営実績その他社会的経済的地位および寄附の相手方など諸般の事 情を考慮して、合理的な範囲内において、その金額等を決すべきであり、右の範囲を越え、不相応な寄附をなすがごときは取締役の忠実義務に違反する。 八幡製鉄株式会社の資本金その他所論の当時における純利益、株主配当金等の額を考慮にいれても、本件寄附が、右の合理的な範囲を越えたものとすることはできないのである。 以上のとおりであるから、被上告人らがした本件寄附は商法二五四条ノ二に定める取締役の忠実義務に違反しない。 |

|
さて、第3回目は、“愛媛県玉串料訴訟”です。 テーマは「政教分離」。 平成11年第18問・平成13年第13問・平成16年第15問に出題されています。 「政教分離」の判例と言えば、まず思い浮かぶのが“あの判例”ですよね? ほら、あれですよ!あれ!! そう、“津地鎮祭事件”。 こちらも、平成13年第13問・平成15年第1問・平成16年第15問と3回も出題されています。 “津地鎮祭事件”の方は皆さん思い浮かぶと思って今回は、あえて“愛媛県…”選んでみました。 これらとともに、「政教分離」三羽烏として“箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟”があります。 平成の間に出題された「政教分離」の判例はこの三つですので、あわせて押さえておくとよいでしょう。 本判決は大きく分けて『支出行為の違法性』と『違法な支出をした知事らの損害賠償責任』の二つの部分から成り、出題されるのは前者の方です。 前者は更に、『政教分離違反となる規範』と『あてはめ』の二つに分かれます。 『政教分離違反となる規範』は例の流れです。 すなわち、「理想は完全分離、だけど現実は関わりを認めざるを得ない。そこで、限界の設定」という流れです。 『あてはめ』では、玉串料・供物料・献灯料の性質や、玉串料等の支出に対する一般人の評価などを考慮して、支出行為が政教分離に反するとしています。 知事らの、 ①県民の要望があること、 ②世俗的になされる香典やさい銭の奉納と変わりがないこと、 を理由とする「玉串料等の奉納が社会的儀礼にすぎない」旨の主張に対して、 最高裁は、これらを検討のうえ斥けています。 |
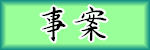
愛媛県が、
を、それぞれ県の公金から支出した。 これらの行為が憲法20条3項・89条等に照らして許されない違法な財務会計上の行為に当たるかどうかが争われた地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償代位請求住民訴訟。 |
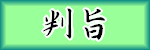
|
一 事実関係及び訴訟の経過 (略) 二 本件支出の違法性に関する当裁判所の判断 1 政教分離原則と憲法二〇条三項、八九条により禁止される国家等の行為 憲法は、二〇条一項後段、三項、八九条において、いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けており、政教分離原則とは、一般に、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。 国家と宗教との関係には、それぞれの国の歴史的・社会的条件によって異なるものがあるが、我が国では、明治憲法の下における信教の自由の保障は不完全なものであったため、憲法は、明治維新以降国家と神道が密接に結び付き種々の弊害を生じたことにかんがみ、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、更にその保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至ったのである。 また、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存する我が国の宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であった。 これらの点にかんがみると、憲法は、政教分離規定を設けるに当たり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものと解すべきである。 しかしながら、元来、政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。 そして、国家が社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の諸施策を実施するに当たって、宗教とのかかわり合いを生ずる ことを免れることはできないから、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近く、政教分離原則を完全に貫こうと すれば、かえって社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れない。 これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いを持たざるを得ないことを前提とした上で、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが問題とならざるを得ないのである。 右のような見地から考えると、憲法の政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教とのかかわり合いを持つことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。 右の政教分離原則の意義に照らすと、憲法二〇条三項にいう宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。 そして、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない。 憲法八九条が禁止している公金その他の公の財産を宗教上の組織又は団体の使用、便益又は維持のために支出すること又はその利用に供することというのも、前記の政教分離原則の意義に照らして、公金支出行為等における国家と宗教とのかかわり合いが前記の相当とされる限度を超えるものをいうものと解すべきであり、これに該当するかどうかを検討するに当たっては、前記と同様の基準によって判断しなければならない。 2 本件支出の違法性 そこで、以上の見地に立って、本件支出の違法性について検討する。 (一)
から、いずれも各神社が宗教的意義を有すると考えていることが明らかなものである。 これらのことからすれば、玉串料等の支出により、県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀にかかわり合いを持ったということが明らかである。 そして、既にその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎない起工式とは異なり、神社自体がその境内において挙行する恒例の重要な祭祀に際して右のような玉串料等を奉納することが、一般人によって社会的儀礼の一つにすぎないと評価されているとは考え難い。 そうであれば、玉串料等の奉納者においても、それが宗教的意義を有するものであるという意識を大なり小なり持たざるを得ない。 また、本件においては、県が他の宗教団体の挙行する同種の儀式に対して同様の支出をしたという事実がうかがわれないのであって、県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない。 これらのことからすれば、地方公共団体が特定の宗教団体に対してのみ特別のかかわり合いを持つことは、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ない。 知事らは、本件支出は、戦没者の慰霊及び遺族の慰謝という世俗的な目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるから、憲法に違反しないと主張する。 確かに、県が公の立場において靖國神社等に祭られている戦没者の慰霊を行うことを望む県民の希望にこたえるという側面においては、本件の玉串料等の奉納に儀礼的な意味合いがあることも否定できない。 しかしながら、たとえ相当数の者がそれを望んでいるとしても、そのことのゆえに、地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが、相当とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえない。 ちなみに、神社に対する玉串料等の奉納が、世俗的目的で贈られる香典との対比で論じられることがあるが、香典は、故人に対する哀悼の意と遺族に対する弔意を表するために遺族に対して贈られ、その葬礼儀式を執り行っている宗教家ないし宗教団体を援助するためのものではないと一般に理解されており、これと宗教団体の行う祭祀に際して宗教団体自体に対して玉串料等を奉納することとでは、一般人の評価において、全く異なるものがあるといわなければならない。 また、知事らは、玉串料等の奉納は、世俗的目的でなされるさい銭の奉納と同様のものであるとも主張するが、地方公共団体の名を示して行う玉串料等の奉納と一般にはその名を表示せずに行うさい銭の奉納とでは、その社会的意味を同一に論じられない。 そうであれば、本件玉串料等の奉納は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても、世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものとは言えない。 以上の事情を総合的に考慮して判断すれば、県が本件玉串料等を靖國神社又は護國神社に前記のとおり奉納したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免 れず、その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、これによってもたらされる県と靖國神社等とのかかわり合いが我が国の社会 的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって、憲法二〇条三項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である。 そうすると、本件支出は、同項の禁止する宗教的活動を行うためにしたものとして、違法というべきである。 (二) また、靖國神社及び護國神社は憲法八九条にいう宗教上の組織又は団体に当たるところ、以上に判示したところからすると、本件玉串料等を靖國神社又は護國 神社に奉納したことによってもたらされる県と靖國神社等とのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものと解されるのであるから、本件支出は、同条の禁止 する公金の支出に当たり、違法というべきである。 三 被上告人らの損害賠償責任の有無 以上のとおり、本件支出は違法であるから、更に進んで、被上告人らの損害賠償責任の有無について検討する。 知事は、東京事務所長・県生活福祉部老人福祉課長らに委任し、又は専決により処理させたのであるから、その指揮監督上の義務に違反し、故意又は過失によりこれを阻止しなかったと認められる場合には、県に対し右違法な支出によって県が被った損害を賠償する義務を負うことになる。 知事は、靖國神社等に対し、東京事務所長・県生活福祉部老人福祉課長らに玉串料等を持参させるなどして、これを奉納したと認められるというのであり、本 件支出には憲法に違反するという重大な違法があること、地方公共団体が特定の宗教団体に玉串料、供物料等の支出をすることについて、文部省、自治省等が、 政教分離原則に照らし、慎重な対応を求める趣旨の通達、回答をしてきたことなどをも考慮すると、その指揮監督上の義務に違反したものであって、これにつき少なくとも過失があったというのが相当である。 したがって、知事は、県に対し、違法な本件支出により県が被った本件支出金相当額の損害を賠償する義務を負う。 これに対し、東京事務所長・県生活福祉部老人福祉課長については、地方自治法二四三条の二第一項後段により損害賠償責任の発生要件が限定されており、本件支出行為をするにつき故意又は重大な過失があった場合に限り県に対して損害賠償責任を負うものであるところ、これらの者は、いずれも委任を受け、又は専決することを任された補助職員として知事の前記のような指揮監督の下で本件支出をしたというのであり、しかも、本件支出が憲法に違反するか否かを極めて容易に判断することができたとまではいえないから、これらの者がこれを憲法に違反しないと考えて行ったことは、その判断を誤ったものではあるが、著しく注意義務を怠ったものとして重大な過失があったということはできない。 そうすると、これらの者(東京事務所長・県生活福祉部老人福祉課長ら)は県に対し損害賠償責任を負わない。 |

|
さて、第4回目は、“特別区区長公選廃止事件”です。 平成9年第14問・平成13年第16問・平成17年第12問に出題されています。 平成7年第8問でも肢の一部として出題されています。 本判決は、最高裁の判決だけ読んだのでは何のための判断だったのかがわかりにくい判決です。 これを知るには、被告人らの主張を見る必要があります。 そこで、本判決での被告人らの主張を整理すると、このようになります。
そして、〔あてはめ〕部で「区議会議員がその区長を選任すること」が憲法第93条第2項に反すると言うには、その前提として、憲法93条2項で渋谷区における区長の直接選挙が保障されていること、すなわち、渋谷区が同条項にいう「地方公共団体」にあたることが言えなければならないのです。 この、『渋谷区が同条項にいう「地方公共団体」にあたる』か?を判断したのが、本判決です。 |
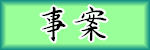
| 被告人らが渋谷区議会議員として区長候補を定め区長を選任するにあたり、金員の提供・授受が行われたことについて、贈収賄罪の成否が問題となった刑事事件。 |
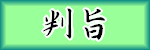
|
憲法は、93条2項において「地方公共団体の長、・・・は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。」と規定している。 憲法が特に一章を設けて地方自治を保障したのは、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となって処理する政治形態を保障せんとする趣旨に出たものである。 この趣旨に徴するときは、右の地方公共団体といい得るためには、事 実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当 程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである。 そして、かかる実体を備えた団体については、その実体を無視して、憲法で保障した地方自治の権能を法律で奪うことは許されない。 東京都の特別区についてこれをみるに、区は、明治以来地方団体としての長い歴史と伝統を有するものではあるが、未だ市町村のごとき完全な自治体としての地位を有していたことはなく、そうした機能を果たしたこともなかつた。 かつて地方自治制度確立に伴い、区の法人格も認められたのであるが、依然として、区長は市長の任命にかかる市の有給吏員とされ、区は課税権、起債権、自治立法権を認められず、単にその財産および営造物に関する事務その他法令により区に属する事務を処理し得るにとどまり、殊に、日華事変以後区の自治権は次第に圧縮され、昭和一八年七月施行の東京都制の下においては、全く都の下部機構たるに過ぎなかつたのである。 戦後、区は、従前の事務のほか法令の定めるところに従い区に属する事務を処理し(一四〇条)、区条例、区規則の制定権、区税および分担金の賦課徴収権が 認められ(一四三条、一五七条ノ三ないし五)、区長公選制も採用することとなり(一五一条ノ二)、翌年制定された地方自治法においても、特別区は「特別地 方公共団体」とし、原則として市に関する規定が適用されることとなつた(二八三条、附則一七条)。 しかし、これら法律の建前が特別区の事務、事業の上にそのまま実現されたわけでなく、政治の実際面においては、区長の公選が実施された程度で,その他は都制下におけるとさしたる変化はなく、特別区は区域内の住民に対して直接行政を執行するとはいえ、その範囲および権限において、市の場合とは著しく趣を異にするところが少なくなかつた。 このことは次に掲げる諸法律の規定に照らして、これを推認し得るに十分である。 すなわち、地方自治法においても、都は条例で特別区について必要な規定を設けることができ(二八二条)、都知事は特別区に都吏員を配置することができる こととした(同法施行令二一〇条)ほか、同法附則二条により現に効力を有する東京都制一九一条の規定に基づき、都制時代に都が処理していた事務の多くのも のが依然として都に留保されていた。 また特別法の規定においても、法律上市に属する事務とされていながら、東京都については、重要な公共事務が特別区の権限からはずされ或いは特別区全体を一つの対象として取扱い、都に市の性格と府県の性格とを併有せしめるものが、数多く認められる。 特に特別区の財政上の権能については、区は、昭和二一年東京都制の一部改正により自主財政権が与えられ、独立して区税を賦課徴収し得ることとなつたが、同年の改正にかかる地方税法においては、区を独立の課税権を有する地方団体としては取り扱わず、昭和二五年の改正地方税法によってもこの建前は変更されることなく、現在に及んでいる。 かように、特別区は昭和二一年九月都制の一部改正によって自治権の拡充強化が図られたにも関わらず、翌年四月制定の地方自治法をはじめその他の法律に よってその自治権に重大な制約が加えられているのは、東京都の戦後における急速な経済の発展、文化の興隆と、住民の日常生活が、特別区の範囲を超えて他の 地域に及ぶもの多く、都心と郊外の昼夜の人口差は次第に甚だしく、区の財源の偏在化も益々著しくなり、二三区の存する地域全体にわたり統一と均衡と計画性 のある大都市行政を実現せんとする要請に基づくものであって、所詮、特別区が、東京都という市の性格をも併有した独立地方公共団体の一部を形成していることに基因するものというべきである。 しかして、特別区の実体が右のごときものである以上、特別区は、憲法制定当時においてもまた昭和二七年八月地方自治法改正当時においても、憲法93条2項の地方公共団体と認めることはできない。 従って、改正地方自治法が右公選制を廃止し、これに代えて、区長は特別区の議会が都知事の同意を得て選任するという方法を採用したからといって、憲法93条2項に違反するものということはできない。 以上 |

|
さて、第5回目は、“警察法改正無効事件”です。 テーマは「司法権の限界」です。 判旨自体は短く、これまで触れてきた判例と比べると“ちょっと一息”といったところでしょうか? 過去問では、平成8年第12問・平成17年第11問・平成18年第14問に出題されています。 平成元年第1問でも、前提として聞かれています。 本判決は、『違法な支出』について支出禁止を求める事ができることを前提に、議会の議決があっても別途支出に違法があれば『違法な支出』になるとし、本件支出が違法となる理由として、
「司法権の限界」として引用される部分は、この理由①に関する判断としてなされたものです。 |
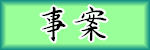
| 大阪府の住民が、府の警察費の支出を違法として、その支出禁止を求めた事件。 |
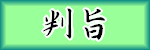
|
地方自治法二四三条の二による住民の監査請求及び訴訟は、議会の議決の是正を目的とするものではない。 しかしながら、長その他の職員による公金の支出等も、法令の規定に従わなければならないのは勿論であり、議会の議決があったからというて、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。 同法が、第五章の議会の解散請求とは別に二四三条の二を規定した趣旨は、個々の住民に、違法支出等の制限、禁止を求める手段を与え、もって、公金の支出、公財産の管理等を適正たらしめる点にある。 とすれば、監査委員は、議会の議決があった場合にも、長に対し、その執行につき妥当な措置を要求することができ、ことに訴訟においては、議決に基づくものでも執行の禁止、制限等を求めることができるものとしなければならない。 上告人が本件支出を違法と主張する理由を見るに、上告人は、警察法が無効である旨を主張し、無効な法律に基づく支出なるが故に違法である旨を主張するのである。 そして上告人は、右警察法を無効と主張する理由として、まず、同法を議決した参議院の議決は無効であって同法は法律としての効力を生じないとするが、同法は両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく同法制定の議事手続に関する所論のような事実を審理してその有効無効を判断すべきでない。 従って所論のような理由によって同法を無効とすることはできない。 次に、同法はその内容において憲法九二条に反するというのであるが、同法が市町村警察を廃し、その事務を都道府県警察に移したからといって、そのことが地方自治の本旨に反するものと解されないから、同法はその内容が憲法九二条に反するものとして無効な法律といいえない。 以上説明のように警察法は無効でなく、上告人は他に本件支出の違法原因を主張するものでないから、上告人の本訴請求は、請求自体理由がないものといわなければならない。 以上 |

|
さて、第6回目は、“薬事法距離制限違憲判決”です。 過去問では、平成元年第5問・平成4年第6問・平成14年第14問・平成16年第11問で出題されています。 今回の判決文は結構長かったため、かなり要約しています(それでもこの長さですが・・・)。 要約にあたっては、原文の意味を損なわないようにできるだけ原文の言葉を用いました。 しかし、要約である以上、原文そのものではありません。 択一対策としては、判決のフレーズの“見覚え”も重要ですので、お手持ちの判例集を参照されるとより効果的に学習できるでしょう。 本判決の全体の枠組みは、
本判決は、許可制の採用が立法府の合理的裁量の範囲内として憲法二二条に反しないといえるためには、「重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置」といえなければならず、さらにそれが消極的、警察的目的でなされる場合には、この他に「許可制よりゆるやかな制限によっては目的を十分に達成することができない」と認められる必要があるとし、この要件を、「許可制を採用すること自体」と「個別の許可基準」のそれぞれについて検討しています。 そして、「個別の許可基準」である“適正配置規制(距離制限)”について必要性・合理性が認められないとして違憲の判断をしています。 |
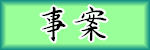
| 医薬品一般販売業の開設許可申請に対してなされた、広島県知事の不許可処分の取消しを求めた行政処分取消請求事件。 |
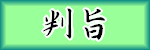
|
一 憲法二二条一項の職業選択の自由と許可制 (一) 職業は、人が自己の生計を維持するためにする継続的活動であるとともに、分業社会においては、これを通じて社会の存続と発展に寄与する社会的機能分担の 活動たる性質を有し、各人が自己のもつ個性を全うすべき場として、個人の人格的価値とも不可分の関連を有するものである。 このような職業の性格と意義に照らすときは、職業は、ひとりその選択、すなわち職業の開始、継続、廃止において自由であるばかりでなく、選択した職業の遂行自体、すなわちその職業活動の内容、態様においても、原則として自由であることが要請されるのであり、したがって、憲法二二条一項は、狭義における職業選択の自由のみならず、職業活動の自由の保障をも包含しているものと解すべきである。 (二) もっとも、職業は、その性質上、社会的相互関連性が大きいものであり、それ自身のうちになんらかの制約の必要性が内在する社会的活動であるが、その種類、性質、内容、社会的意義及び影響がきわめて多種多様であるため、その規制を要求する社会的理由ないし目的も、社会政策及び経済政策上の積極的なものから、消極的なものに至るまで千差万別で、その重要性も区々にわたるのである。 そしてこれに対応して、現実に職業の自由に対して加えられる制限も、それぞれの事情に応じて各種各様の形をとることとなるのである。 それ故、これらの規制措置が憲法二二条一項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは、これを一律に論ずることができず、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量したうえで慎重に決定されなければならない。 この場合、右のような検討と考量をするのは、第一次的には立法府の権限と責務であり、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められ る以上、そのための規制措置の具体的内容及びその必要性と合理性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまるかぎり、立法政策上の問題とし てその判断を尊重すべきものである。 しかし、右の合理的裁量の範囲については、事の性質上おのずから広狭がありうるのであって、裁判所は、具体的な規制の目的、対象、方法等の性質と内容に照らして、これを決すべきものといわなければならない。 (三) 職業の許可制は、職業の自由に対する公権力による制限の一態様である。 一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。 そして、この要件は、許可制の採用自体が是認される場合であっても、個々の許可条件について、更に個別的に右の要件に照らしてその適否を判断しなければならないのである。 二 薬事法における許可制について。 (一) 薬事法は、医薬品等に関する事項を規制し、その適正をはかることを目的とし、医薬品等の供給業務に関して広く許可制を採用している。 医薬品が、国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとともに、これと至大の関係を有するものであることからすれば、不良医薬品の供給(不良調剤を含 む。以下同じ。)から国民の健康と安全とを守るために、業務の内容の規制のみならず、供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による 開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる。 (二) そこで進んで、許可条件に関する基準をみると、薬事法二六条二項によって医薬品の一般販売業に準用される薬事法六条は、二項において、設置場所の配置の適正の観点から許可をしないことができる場合を認め、四項においてその具体的内容を都道府県の条例に譲っている。 そこで、以下において適正配置上の観点から不許可の道を開くこととした趣旨、目的を明らかにし、このような許可条件の設定とその目的との関連性、及びこのような目的を達成する手段としての必要性と合理性を検討し、この点に関する立法府の判断がその合理的裁量の範囲を超えないかどうかを判断することとする。 三 薬局及び医薬品の一般販売業(以下「薬局等」という。)の適正配置規制の立法目的及び理由について。 (一) 薬事法六条二項、四項の適正配置規制に関する規定は、「薬事法の一部を改正する法律」により、新たな薬局の開設等の許可条件として追加されたものである が、右の改正法律案の提案理由、薬事法の性格及びその規定全体との関係からみても、一部地域における薬局等の乱設による過当競争のために一部業者に経営の 不安定を生じ、その結果として施設の欠陥等による不良医薬品の供給の危険が生じるのを防止すること、及び薬局等の一部地域への偏在の阻止によって無薬局地域又は過少薬局地域への薬局の開設等を間接的に促進することの二点が右の適正配置規制の目的であり、その中でも前者がその主たる目的をなし、後者は副次的、補充的目的であるにとどまると考えられる。 これによると、右の適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的のための規制措置であり、そこで考えられている薬局等の過当競争及びその経営の不安定化の防止も、あくまでも不良医薬品の供給の防止のための手段であるにすぎないものと認められる。 また、一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によって強い規制を 施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合があるけれども、薬事法その他の関係法令は、そのような強力な規制を施していないので、その反面において既存の薬局等にある程度の独占的地位を与える必要も理由もなく、本件適正配置規制にはこのような趣旨、目的はなんら含まれていないと考えられるのである。 (二) 略 四 適正配置規制の合憲性について。 (一) 薬局の開設等の許可条件として地域的な配置基準を定めた目的が不良医薬品の供給の危険が生じるのを防止すること、及び無薬局地域又は過少薬局地域への薬 局の開設等を間接的に促進することにあるとすれば、それらの目的は、いずれも公共の福祉に合致するものであり、かつ、それ自体としては重要な公共の利益と いうことができるから、右の配置規制がこれらの目的のために必要かつ合理的であり、薬局等の業務執行に対する規制によるだけでは右の目的を達することができないと言えれば、許可条件の一つとして地域的な適正配置基準を定めることは、憲法二二条一項に違反するものとはいえない。 (二) 薬局等の設置場所についてなんらの地域的制限が設けられない場合、薬局等が都会地に偏在し、これに伴って業者間に過当競争が生じ、その結果として一部業者の経営が不安定となるような状態が生じる可能性がある。 しかし、このことから、医薬品の供給上の著しい弊害が、薬局の開設等の許可につき地域的規制を施すことによって防止しなければならない必要性と合理性を肯定させるほどに生じているものと合理的に認められるかどうかについては、更に検討を必要とする。
以上のとおり、薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法二二条一項に違反し、無効である。 以上 |

|
さて、第7回目は、“小売市場事件”です。 過去問では、平成4年第6問・平成8年第19問・平成12年第16・17問・平成14年第6問・平成16年第11問で出題されています。 メジャーな判例だけあって、かなりの出題数となっています。 前回の“薬事法距離制限違憲判決”と同様、経済的自由権に関する判例ですが、 “薬事法距離制限違憲判決”では、距離制限が『不良医薬品の供給の危険が生じるのを防止』するという消極目的でなされているとしており、『薬局等の過当競争及びその経営の不安定化の防止』という点に触れてはいるものの、『あくまでも不良医薬品の供給の防止のための手段であるにすぎない』としています。 これに対して本判決は、規制目的を『小売市場の乱設に伴う小売商相互間の過当競争によって招来されるのであろう小売商の共倒れから小売商を保護するため』の積極目的であるとしているという違いがあります。 本件で被告人は、知事の許可を得ずに建物を小売商に貸し付ける行為を罰する小売商業調整特別措置法二二条一号が、憲法に反し無効であるとして無罪を主張しています。 具体的には、 ①小売市場の開設経営を知事の許可にかからしめている点で、営業の自由を保障する憲法二二条一項に反する。 ②指定都市の小売市場のみを規制の対象としている点で、憲法一四条に反する。 ③「十店舗未満の小売市場」および「スーパーマーケット」を規制の対象としていない点で、憲法一四条に反する。 というものです。 他に憲法二五条一項違反の主張もなされていますが、これといった判断はなされていないので、省略しました。 |
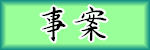
| 被告人が、小売商業調整特別措置法3条に基づく政令指定地域において、知事の許可を得ることなく、その所有する建物を小売商に貸し付けたとして起訴された刑事事件。 |
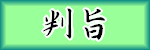
|
(①の点について) 小売商業調整特別措置法は、同法所定の市の区域内で、同法所定の形態の小売市場を開設経営しようとする者に、同法所定の許可を受けることを要求し、かつ、同法五条各号に掲げる事由がある場合には、右許可をしないものとしているので、小売市場の開設経営をしようとする者の営業の自由を制限するものである。 そこで、右の営業の自由に対する制限が憲法二二条一項に抵触するかどうかについて考察することとする。 憲法二二条一項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障し、そこには営業の自由も含まれており、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものということができる。 しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、右条項自体の明示するところである。 そして、右条項に基づく個人の経済活動に対する法的規制が、 個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害を除去ないし緩和するための消極的規制として、必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことはいうまでもない。 のみならず、憲法が、全体として、福祉国家的理想のもとに、社会経済の均衡のとれた調和的発展を企図していることなどからすると、憲法は、国の責務として積極的な社会経済政策の実施を予定しているものということができ、 個人の経済活動の自由に関する限り、個人の精神的自由等に関する場合とは異なり、右社会経済政策の実施の一手段として、これに一定の合理的規制措置を講ずることは、もともと、憲法が予定し、かつ、許容するところと解される。 国は、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、もつて社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るために、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規制措置を講ずることができる。 もっとも、個人の経済活動に対する法的規制には、その規制の対象、手段、態様等において自ら一定の限界が存するものと解するのが相当である。 ところで、法的規制措置の必要の有無や法的規制措置の対象・手段・態様などの判断にあたっては、 対象となる社会経済の実態についての正確な基礎資料が必要であり、具体的な法的規制措置が現実の社会経済にどのような影響を及ぼすか、その利害得失を洞察するとともに、広く社会経済政策全体との調和を考慮する等、 相互に関連する諸条件についての適正な評価と判断が必要であるが、 このような評価と判断の機能を果たす適格を具えているのは立法府であるから、立法府の裁量的判断にまつほかない。 したがって、右に述べたような個人の経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはなく、 裁判所は、立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である。 これを本件についてみると、 本法は、立法当時における中小企業保護政策の一環として成立したものであり、 本法所定の小売市場を許可規制の対象としているのは、小売商が国民のなかに占める数と国民経済における役割とに鑑み、本法一条の立法目的が示すとおり、経 済的基盤の弱い小売商の事業活動の機会を適正に確保し、かつ、小売商の正常な秩序を阻害する要因を除去する必要があるとの判断のもとに、その一方策とし て、小売市場の乱設に伴う小売商相互間の過当競争によって招来されるのであろう小売商の共倒れから小売商を保護するためにとられた措置であると認められ、 一般消費者の利益を犠牲にして、小売商に対し積極的に流通市場における独占的利益を付与するためのものでないことが明らかである。 しかも、本法は、その所定形態の小売市場のみを規制の対象としているにすぎないのであって、小売市場内の店舗のなかに政令で指定する野菜、生鮮魚介類を販 売する店舗が含まれない場合とか、所定の小売市場の形態をとらないで右政令指定物品を販売する店舗の貸与等をする場合には、これを本法の規制対象から除外 するなど、過当競争による弊害が特に顕著と認められる場合についてのみ、これを規制する趣旨であることが窺われる。 これらの諸点からみると、本法所定の小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、 また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない。 そうすると、本法三条一項、同法施行令一条、二条所定の小売市場の許可規制は憲法二二条一項に違反するものとすることができない。 (②の点について) 本法三条一項、同法施行令一条および別表一がその指定する都市の小売市場に限って規制の対象としたのは、 小売市場の当該地域社会において果たす役割、当該地域における小売市場乱設の傾向等を勘案し、本法の上記目的を達するために必要な限度で規制対象都市を限定したものであって、その判断が著しく合理性を欠くことが明白であるとはいえないから、 その結果として、小売市場を開設しようとする者の間に、地域によって規制を受ける者と受けない者との差異が生じたとしても、そのことを理由として憲法一四条に違反するものとすることはできない。 (③の点について) 本法所定の小売市場以外の小売市場を規制の対象とするかどうか、スーパーマーケットを規制の対象とするかどうかは、いずれも立法政策の問題であって、これらの規制の対象としないからといって、そのために本法の規制が憲法一四条に違反することになるわけではない。 以上 |

|
さて、第8回目は、“博多駅テレビフィルム提出命令事件”です。 過去問では、平成7年第9問・平成11年第6問・平成13年第17問・平成17年第7問・平成18年第10問で出題されています。 出題回数もさることながら、直近の2年に連続して出題されているという特徴があります。 さて判旨の全体構造ですが、 提出命令が、報道機関の“将来の”取材活動に影響を与えうることを前提に、 ⅰ)取材の自由は憲法二一条の精神に照らし十分尊重に値する。 ↓もっとも、 ⅱ)取材の自由も公正な刑事裁判の実現のため必要があるときには、ある程度の制約を受ける。そしてこの制約は、『やむを得ない場合』に許容されるが、それは比較衡量によって判断する。 ↓本件では、 ①取材フィルムは被疑者らの罪責の有無を判定するうえで、ほとんど必須のものと認められること(証拠としての必要性)。 ②他方、報道機関の不利益は将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまること(取材の自由が妨げられる程度)。 ③裁判所も、報道機関のフィルム使用に支障をきたさないよう配慮する旨を表明していること(報道機関の不利益への配慮)。 から、『やむを得ない場合』といえるので、提出命令は二一条に反しない。 というものです。 このうち、ⅰ)の部分はよくひっかけで聞かれるところですね。 「判例は、報道機関の取材の自由が憲法21条で保障されるとしている。」とか“しれっと”書いてあるんですね。肢をよく読まずに読み飛ばしたりしているとひっかかるんです。 判旨の方では「取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値する」となっています。 こんな古典的な伏兵にやられている場合ではありませんので気をつけてください。 |
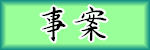
| 付審判請求の審理にあたってなされた裁判所の提出命令に対して、それを受けた放送局側が報道の自由を侵害するとして争った事件。 |
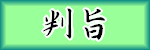
|
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。 したがって、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。 また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない。 ところで、本件提出命令の対象とされたのは、取材活動の結果すでに得られたものであるから、その提出を命ずることは、現に行われた取材活動そのものとは直接関係がない。 もっとも、提出命令は、取材テープを刑事裁判の証拠として使用するという本来の目的以外の目的で使用することであるから、報道機関の将来における取材活動の自由を妨げるおそれがないわけではない。 しかし、取材の自由といっても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることのあることも否定することができない。 本件では、まさに、公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が許されるかどうかが問題となるのであるが、 公正な刑事裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、刑事裁判においては、実体的真実の発見が強く要請されることもいうまでもない。 このような公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によって得られたものの証拠としての必要性が認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなってもやむを得ないところというべきである。 しかしながら、このような場合においても、 一面において、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたっての必要性の有無を考慮するとともに、 他面において取材したものを証拠として提出させられることによって報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、 これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合においても、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。 以上の見地に立って本件についてみるに、 本件の付審判請求事件の審理の対象は、多数の機動隊等と学生との間の衝突に際して行なわれたとされる機動隊員等の公務員職権乱用罪、特別公務員暴行陵虐罪の成否にある。 その審理は、現在において、被疑者および被害者の特定すら困難な状態であって、 事件発生後二年ちかくを経過した現在、第三者の新たな証言はもはや期待することができず、 したがって、当時、右の現場を中立的な立場から撮影した報道機関の本件フィルムが証拠上きわめて重要な価値を有し、被疑者らの罪責の有無を判定するうえに、ほとんど必須のものと認められる状況にある。 他方、本件フィルムは、すでに放映されたものを含む放映のために準備されたものであり,それが証拠として使用されることによって報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにとどまるものと解されるのであって、 付審判請求事件とはいえ、本件の刑事裁判が公正に行なわれることを期するためには、この程度の不利益は、報道機関の立場を十分尊重すべきものとの見地に立つても、なお忍受されなければならない程度のものというべきである。 また、本件提出命令を発した福岡地方裁判所は、本件フィルムにつき、一たん押収した後においても、時機に応じた仮還付などの措置により、報道機関のフィルム使用に支障をきたさないより配慮すべき旨を表明している。 以上の諸点その他各般の事情をあわせ考慮するときは、本件フィルムを付審判請求事件の証拠として使用するために本件提出命令を発したことは、まことにやむを得ないものがあると認められるのである。 前叙のように考えると、本件フィルムの提出命令は、憲法二一条に違反するものでない。 以上 |

|
さて、第9回目は、“川崎民商税務検査拒否事件”です。 本判決では、 (1)旧所得税法七〇条一〇号の罪の内容をなす同法六三条は規定が不明確であり、憲法三一条に反しないか? (2)収税官吏による検査は、「令状を要求しない」点で憲法三五条に反しないか? (3)収税官吏による質問は、「不利益な供述を強要する」点で憲法三八条に反しないか? が問題となっています。 択一対策としては、下記の《判旨》のところで強調してあるポイントを中心に押さえてもらえればよいでしょう。 さて、ここから先は“大人の時間”ですので、興味のある人だけ読んでください。 上に挙げた(2)については、実は結構分かりにくいものとなっています。 結論としては、『令状が要求されない収税官吏による検査も、憲法三五条に反しない。』でいいのですが、そこに至る過程がはっきりしていません。 理論的には、 ⅰ)憲法35条は刑事手続以外の手続きにも適用されるが、“収税官吏による検査”には適用がないので、令状がなくても同条に反しない。 ⅱ)憲法35条は刑事手続以外の手続きにも適用され“収税官吏による検査”にも適用されるが、同条は例外的に令状を要しない場合を認めており、“収税官吏による検査”の場合はこれにあたるので、令状なくても同条に反しない。 の2通り考えられると思います(私見ですが・・・)。 判旨からはいずれともはっきりしません。
①38条について、『右規定による保障は、純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶ』としていること ②『収税官吏の検査は、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、また実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでもない』としていること ③仮にⅱ)の構成を採ると、35条について“令状が必要になる手続き”と“令状が必要でない手続き”を認めることになり、令状主義に「例外」という風穴を開けることになってしまうこと からすると、ⅰ)の構成ではないかと考えます。
|
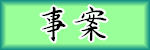
|
被告人が、税務調査に来た税務署職員に対して帳簿書類の呈示を拒んだことから、旧所得税法に違反するとして起訴された刑事事件。 |
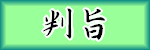
| 上告趣意第一点について。 旧所得税法七〇条一〇号の罪の内容をなす同法六三条は、規定の意義が不明確であって、憲法三一条に違反するものである旨主張する。 しかし、第一、第二審判決判示の本件事実関係からすれば、 税務署職員の職務上の地位および行為が旧所得税法六三条所定の各要件を具備するものであることは明らかであるから、 旧所得税法七〇条一〇号の刑罰規定の内容をなす同法六三条の規定は、それが本件に適用される場合に、その内容になんら不明確な点は存しない。 上告趣意第二点について。 (憲法三五条違反について) 旧所得税法七〇条一〇号、六三条の規定が裁判所の令状なくして強制的に検査することを認めているのは憲法三五条に違反する旨主張する。 たしかに、旧所得税法七〇条一〇号の規定する検査拒否に対する罰則は、同法六三条所定の収税官吏による当該帳簿等の検査の受忍をその相手方に対して強制する作用を伴うものである。 しかし、 同法六三条所定の収税官吏の検査は、もつぱら、所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であって、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない。 また、右検査の結果、所得税逋脱の事実が発覚する可能性もあるが、 検査の範囲が、前記の目的のため必要な所得税に関する事項にかぎられていること、 また、その検査は、所得税の賦課徴収手続上一定の関係にある者につき、その者の事業に関する帳簿その他の物件のみを対象とするもので、所得税の逋脱等、刑事責任の嫌疑を基準に右の範囲が定められているわけではないこと からすれば、右検査が、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものと認めるべきことにはならない。 さらに、この場合の強制の態様は、 収税官吏の検査を正当な理由がなく拒む者に対し、同法七〇条所定の刑罰を加えることによって、間接的心理的に右検査の受忍を強制しようとするものであり、 かつ、 その作用する強制の度合いは、それが検査の相手方の自由な意思をいちじるしく拘束して、実質上、直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたいところである。 国家財政の基本となる徴税権の適正な運用を確保し、所得税の公平確実な賦課徴収を図るという公益上の目的を実現するために収税官吏による実効性のある検査制度が欠くべからざるものであることは、何人も否定しがたいものであるところ、その目的、必要性にかんがみれば、右の程度の強制は、実効性確保の手段として、あながち不均衡、不合理なものとはいえないのである。 憲法三五条一項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、 当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。 しかしながら、前に述べた諸点を総合して判断すれば、旧所得税法七〇条一〇号、六三条に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといって、これを憲法三五条の法意に反するものとすることはできず、前記規定を違憲であるとする所論は、理由がない。 (憲法三八条違反について) 検査、質問の結果、所得税逋脱の事実が明らかになれば、税務職員は右の事実を告発できるのであるから、右検査、質問は、刑事訴追をうけるおそれのある事項につき供述を強要するもので憲法三八条に違反する旨主張する。 しかし、同法七〇条一〇号、六三条に規定する検査が、もっぱら所得税の公平確実な賦課徴収を目的とする手続であって、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、また、そのための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでもないこと、 および、 このような検査制度に公益上の必要性と合理性の存すること は、同法七〇条一二号、六三条に規定する質問も同様であると解すべきである。 そして、憲法三八条一項の法意は、何人も自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものであると解すべきであるが、 右規定による保障は、純然たる刑事手続においてばかりではなく、それ以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶものと解する。 しかし、旧所得税法七〇条一〇号、一二号、六三条の検査、質問の性質が上述のようなものである以上、右各規定そのものが憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」を強要するものとすることはできず、この点の所論も理由がない。 |

| さて、第10回目は、"旭川学テ事件"です。 今回は今までにない超大作となっていますので覚悟してください。 過去問では、平成10年第13問・平成12年第10問・平成17年第17問で出題され、平成7年第10問でも前提として問われています。 本判決の全体的な構造は、 公務執行妨害罪が成立するには「職務の適法性」が必要であることを前提に、 本件学力調査が "手続的に違法"となるか? "実質上違法"となるか?を検討しています。 "手続的違法"として、 ⅰ)本件学力調査は、地教行法五四条二項の許容する行政調査を超えており違法 ⅱ)地教行法五四条二項は文部大臣に学力調査の実施を要求する権限を認めていないので、文部大臣の要求に応じてなされた本件学力調査は違法 の2点を検討しています。 ⅰ)では、学力調査が行政調査であることを前提に、本件学力調査の方法が「試験」によって行われたために教育活動としての性格を帯び、行政調査として許容される範囲を超えたのではないかが問題とされています(←ここで『本件学力調査が…行政調査として行われた』との判断が示されています。)。 また、"実質上違法"として、 ⅰ)本件学力調査は「不当な支配」にあたり違法 ⅱ)文部大臣が地教委に学力調査をさせたことが教育の地方自治の原則に反し違法 の2点を検討しています。 この判例で最も有名な『教育内容決定権の所在』の判断は、 ⅰ)の学力調査が「不当な支配」にあたるかを判断するにあたり、そもそも国家はどの程度教育に介入できるのかを明らかにするためになされました。 |
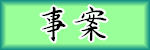
| 被告人らが、全国一斉学力調査を実力で阻止しようとした行為が公務執行妨害罪等で起訴された刑事事件。 |
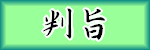
| 三 本件学力調査と地教行法五四条二項(手続上の適法性) (一)本件学力調査においてとられた「試験問題によって生徒を試験するという方法」が、教師の行う教育活動の一部としての試験とその形態を同じくするものであることは確かであるが、 本件学力調査は、あくまでも全国の中学生の学力が一般的にどの程度のものであるかを調査するためになされるものであって、 両者の間には、その趣旨と性格において明らかに区別があるのである。 したがって地教行法五四条二項にいう行政調査のわくを超えた違法なものとは言えない。 (二)文部省が地教行法五四条二項の規定を根拠に本件学力調査の実施を要求することはできないが、そのために右要求に応じて行われた地方公共団体の教育委員会(以下「地教委」という。)の調査行為が当然に手続上違法となるわけではない。 地教委は、当該地方公共団体の教育にかかる調査をする権限を有しているので、本件において旭川市教育委員会が旭川市立の各中学校につき実施した調査行為は、少なくとも手続法上は権限なくしてなされた違法なものとはいえない。 そして、市町村教育委員会は、その管理権に基づき、特に必要な場合には具体的な命令を発することもできるので、 旭川市教育委員会が、各中学校長に対し、テストの実施を命じたことも、手続的には適法な権限に基づくものといえ、本件学力調査の実施には手続上の違法性はないというべきである。 四 本件学力調査と教育法制(実質上の適法性) そこで、以下においては、このような立場から本件学力調査が教基法一〇条を含む現行の教育法制及びそれから導かれる法理に違反するかどうかを検討することとする。 1 子どもの教育と教育権能の帰属の問題 (一)教基法一〇条の解釈に関する問題を考察するにあたっては、 広く、わが国において憲法以下の教育関係法制が 国家の教育に対する支配ないし介入の当否及びその限界という問題に対して、いかなる態度をとっているかという全体的な観察の下で、これを行わなければならない。 (二)ところで、わが国の法制上、子どもの教育の内容を決定する権能が誰に帰属するとされているかについては、二つの極端に対立する見解がる。 すなわち、 一の見解は…(国家教育権説)と主張する。 これに対し、 他の見解は…(国民教育権説)と主張するのである。 当裁判所は、右の二つの見解はいずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできないと考える。 以下に、その理由と当裁判所の見解を述べる。 2 憲法と子どもに対する教育権能 (一)憲法二六条は、親に対し、その子女に普通教育を受けさせる義務を課し、かつ、その費用を国において負担すべきことを宣言したものであるが、 この規定の背後には、 国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、 特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる。 換言すれば、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられているのである。 しかしながら、このことから、教育の内容及び方法を、誰がいかにして決定すべく、また、決定することができるかという問題に対する一定の結論は、当然には導き出されない。 (二)次に、憲法二三条により、教師は教授の自由を有し、自由に子どもの教育内容を決定することができるとする見解も、採用することができない。 確かに、学問の自由は、教授の自由をも含むと解されるし、 更にまた、普通教育の場においても、一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない。 しかし、 大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、 普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、 また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、 普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることはできない。 (三)子どもにどのような教育を施すかは、その子どもの将来に決定的な役割をはたすものである。 それ故、子どもの教育の結果に利害と関心をもつ関係者が、それぞれの立場からその決定、実施に対する支配権ないしは発言権を主張するのは、極めて自然な成行きということができる。 子どもの教育は、専ら子どもの利益のために行われなければならないが、何が子どもの利益であり、また、そのために何が必要であるかについては、関係者の間で意見の対立が当然に生じうるのであって、 そのために教育内容の決定につき矛盾、対立する主張の衝突が起こるのを免れない。 このような矛盾対立を解決するには、右関係者らのそれぞれの主張がよって立つ憲法上の根拠に照らして各主張の妥当すべき範囲を画するのが、最も合理的な解釈である。 そこで、 まず親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対して最も深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるものと考えられるし、 また、私学教育における自由や前述した教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲においてこれを肯定するのが相当であるけれども、 それ以外の領域においては、一般に社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益を擁護するため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有するものと解さざるをえない。 もとより、教育は、党派的な政治的観念や利害によって支配されるべきではないから、そこに政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、 教育内容に対する右のごとき国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、 教育にそのような殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤った知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法二六条、一三条の規定上からも許されないと解することができるけれども、 これらのことは、前述のような子どもの教育内容に対する国の正当な理由に基づく合理的な決定権能を否定する理由となるものではないといわなければならない。 3 教基法一〇条の解釈 次に、憲法における教育に対する国の権能及び親、教師等の教育の自由についての上記のような理解を背景として、教基法一〇条の規定をいかに解釈すべきかを検討する。 (一)教基法は、 憲法に代わって、わが国の教育及び教育制度全体を通じる基本理念と基本原理を宣明することを目的として制定されたものであって、 戦後、教育の根本的改革を目途として制定された諸立法の中で中心的地位を占める法律であるから、教育関係法令の解釈及び運用にあたっては、法律自体に別段の規定がない限り、できるだけ教基法の規定及び同法の趣旨、目的に沿うように考慮が払われなければならないというべきである。 教基法は、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的で、しかも個性豊かな文化の創造をめざす教育が今後におけるわが国の教育の基本理念であるとしているが、これは、同法の各規定を解釈するにあたって強く念頭に置かれるべきものである。 (二)本件で問題とされている教基法一〇条につき、 (1)第一に、教育行政機関が法令に基づいて行政を行う場合が、右教基法一〇条一項にいう「不当な支配」に含まれないと解すべきかどうか、 (2)第二に、同条二項にいう「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」とは、主として教育施設の設置管理、教員配置等のいわゆる教育の外的事項に関するものを指し、教育課程、教育方法等のいわゆる内的事項については、教育行政機関の権限は原則としてごく大綱的な基準の設定に限られ、その余は指導、助言的作用にとどめられるべきものかどうか、 という問題がある。 (三)まず、(1)の問題について考えるのに、 教基法一〇条一項は、教育は、国民の信託にこたえて国民全体に対して直接責任を負うように行われるべきであり、その間において不当な支配によってゆがめられることなく、教育が専ら教育本来の目的に従って行われるべきことを示したものと考えられることから、 同条項が排斥しているのは、教育が国民の信託にこたえて右の意味において自主的に行われることをゆがめるような「不当な支配」であって、その主体のいかんは問うところでないといえる。 それ故、論理的には、教育行政機関が行う行政でも、右にいう「不当な支配」にあたる場合がありうる。 問題は、教育行政機関が法令に基づいてする行為が「不当な支配」にあたる場合がありうるかということに帰着する。 思うに、他の教育関係法律は教基法の規定及び同法の趣旨、目的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、教基法一〇条一項にいう「不当な支配」とならないように配慮しなければならない拘束を受けており、 その意味において、教基法一〇条一項は、法令に基づく教育行政機関の行為にも適用があるものといわなければならない。 (四)そこで、次に、上記(2)の問題について考えるのに、 子どもの教育が、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、子どもの個性に応じて弾力的に行われなければならず、そこに教師の自由な創意と工夫の余地が要請されること、 また、教基法が戦前における教育に対する過度の国家的介入、統制に対する反省から生まれたものであること から、同法一〇条が教育に対する権力的介入、特に行政権力によるそれを警戒し、これに対して抑制的態度を表明したものと解することにも、それなりの合理性はあるが、このことから、教育内容に対する行政の権力的介入が一切排除されているものとはいえない。 教基法一〇条は、 国の教育統制権能を前提としつつ、教育行政の目標を教育の目的の遂行に必要な諸条件の整備確立に置き、 そのための措置を講ずるにあたり、教育の自主性尊重の見地から、これに対する「不当な支配」となることのないようにすべき旨の限定を付したところにその意味があり、 したがって、教育に対する行政権力の不当、不要の介入は排除されるべきであるとしても、許容される目的のために心要かつ合理的と認められる介入は、たとえ教育の内容及び方法に関するものであっても、必ずしも同条の禁止するところではないと解する。 思うに、国の教育行政機関が、法律の授権に基づいて義務教育に属する普通教育の内容及び方法について遵守すべき基準を設定する場合には、 教師の創意工夫の尊重等教基法一〇条に関してさきに述べたところのほか、 後述する教育に関する地方自治の原則をも考慮し、 右教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的なそれにとどめられるべきものと解しなければならない。 これを文部大臣の定めた中学校学習指導要領についていえば、 文部大臣は、 学校教育法三八条、一〇六条による中学校の教科に関する事項を定める権限に基づき、 普通教育に属する中学校における教育の内容及び方法につき、上述のような教育の機会均等の確保等といった目的のために必要かつ合理的な基準を設定することができるものと解すべきところ、 本件当時の中学校学習指導要領の内容を通覧するのに、 おおむね、中学校において地域差、学校差を超えて全国的に共通なものとして教授されることが必要な最小限度の基準と考えても必ずしも不合理とはいえない事項が、その根幹をなしていると認められる。 中には、合理性が疑わしいものが幾分含まれているとしても、 右指導要領の下における 教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており、 全体としてはなお全国的な大綱的基準としての性格をもつものと認められるし、 また、その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていないのである。 それ故、上記指導要領は、少なくとも法的見地からは、上記目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるものと解するのが、相当である。 4 本件学力調査と教基法一〇条 本件学力調査が行政調査として教基法一〇条との関係において適法とされうるかどうかを判断するについては、 ①その調査目的において文部大臣の所掌とされている事項と合理的関連性を有するか、 ②右の目的のために本件のような調査を行う必要性を肯定することができるか、 ③本件の調査方法に教育に対する不当な支配とみられる要素はないか 等の問題を検討しなければならない。 (一)まず、本件学力調査の目的(要件①)についてみるのに、 右調査の実施要綱には、調査目的として四つの項目が挙げられているが、 このうちの3つ(イ)(ハ)(ニ)については、 文部大臣が、全国中学校における教育の機会均等の確保、教育水準の維持、向上に努め、教育施設の整備、充実をはかる責務と権限を有することからすれば、 これらの権限と合理的関連性を有するものと認めることができるし、 右目的に附随して、地教委をしてそれぞれの所掌する事項に調査結果を利用させようとすることも、文部大臣の地教委に対する指導、助言的性格のものとして不当ということはできない。 また、右四項目中 (ロ)の、中学校において、本件学力調査の結果により、自校の学習の到達度を全国的な水準との比較においてみることにより、その長短を知り、生徒の学習の指導とその向上に役立たせる資料とするという項目は、 それが文部大臣固有の行政権限に直接関係せず、中学校における教育実施上の目的に資するためのものである点において、調査目的として正当性を有するかどうか問題であるけれども、 右は、本件学力調査全体の趣旨、目的からいえば、単に副次的な意義をもつものでしかないと認めるのが相当であるのみならず、調査結果を教育活動上利用すべきことを強制するものではなく、指導、助言的性格のものにすぎず、これをいかに利用するかは教師の良識ある判断にまかされるべきものと考えられるから、 右の(ロ)が調査目的の一つに掲げられているからといって、調査全体の目的を違法不当のものとすることはできないというべきである。 (二)次に、本件学力調査は、 文部省が当時の中学校学習指導要領によって試験問題を作成し、全国の中学校の全部において一斉に右問題による試験を行い、各地教委にその結果を集計、報告させる等の方法によって行われたものであるが、 このような方法による調査が前記の調査目的のためと認めることができるかどうか(要件②)、及び教育に対する不当な支配の要素をもつものでないかどうか(要件③)は、慎重な検討を要する問題である。 まず、必要性の有無(要件②)について考えるのに、 全国の中学校における生徒の学力の程度が、どの程度のものであり、そこにどのような不足ないしは欠陥があるかを知ることは、上記の(イ)、(ハ)、(ニ)に掲げる諸施策のための資料として必要かつ有用であることは明らかであり、 また、このような学力調査の方法としては、結局試験によってその結果をみるよりほかにはないのであるから、文部大臣が全国の中学生の学力をできるだけ正確かつ客観的に把握するためには、全国の中学校の生徒に対し同一試験問題によって同一調査日に同一時間割で一斉に試験を行うことが必要であると考えたとしても、決して不合理とはいえない。 それ故、本件学力調査は、その必要性の点において欠けるところはないというべきである。 (三)問題となるのは、上記のような方法による調査が、 その一面において文部大臣が直接教育そのものに介入するという要素を含み、 また、右に述べたような調査の必要性によっては正当化することができないほどに教育に対して大きな影響力を及ぼし、これらの点において文部大臣の教育に対する「不当な支配」となるものではないか(要件③)、ということである。 まず、本件学力調査は、あくまでも生徒の一般的な学力の程度を把握するためのものであって、教育活動そのものとは性格を異にするものである。 もっとも、試験という形態をとる以上、学力調査目的でされたものが成績評価目的に利用される可能性はあり、現に本件学力調査においても、試験の結果を生徒指導要録に記録させることとしている点からみれば、両者の間における一定の結びつきの存在を否定することはできないが、この点は、せつかく実施した試験の結果を生徒に対する学習指導にも利用させようとする指導、助言的性格のものにすぎないとみるべきであるから、 以上の点をもって、 文部省自身が教育活動を行ったとも、教師に対して一定の成績評価を強制し、教育に対する実質的な介入をしたとも言えない。 また、試験実施のために試験当日限り各中学校における授業計画の変更を余儀なくされることになるが、年間の授業計画全体に与える影響についてみれば、それは、実質上各学校の教育内容の一部を強制的に変更させる意味をもつほどのものとはいえず、前記のような本件学力調査の必要性によって正当化することができる。 次に、もともと右学習指導要領自体が全体としてみて適法なものであり、これによって必ずしも教師の教育の自由を不当に拘束するものとは認められず、 本件学力調査は、生徒の一般的な学力の実態調査のために行われたもので、学習指導要領の遵守を強制ないしは促進するために行われたものではなく、 右指導要領は、単に調査のための試験問題作成上の基準として用いられたにとどまっているのである。 もっとも、右調査の実施によって、成績競争という教育上必ずしも好ましくない状況が生じ、また、教師の真に自由で創造的な教育活動を畏縮させるおそれが絶無ではなく、教育政策上はたして適当な措置であるかどうかについて問題があるばかりか、試験の結果を生徒指導要録の標準検査の欄に記録させることとしている点については、特にその妥当性に批判の余地があるが、 本件学力調査実施要綱によれば、同調査においては、特別の準備を要しない全体として平易な試験問題を使用し、また、調査結果は公表しないこととされる等一応の配慮が加えられていたことや、 教師の教育の自由が阻害される危険性も、教師自身を含めた教育関係者、父母、その他社会一般の良識を前提とする限り、それが全国的に現実化する可能性はそれほど強いとは考えられないこと等を考慮するときは、 法的見地からは、本件学力調査が、前記目的のための必要性をもってしても正当化することができないほどの教育に対する強い影響力、支配力をもち、教基法一〇条にいう教育に対する「不当な支配」にあたるものとすることは、相当ではなく、本件学力調査は、その調査の方法において違法であるということはできない。 (四)以上説示のとおりであって、本件学力調査には、教育そのものに対する「不当な支配」として教基法一〇条に違反する違法があるとすることはできない。 5 本件学力調査と教育の地方自治 (一)思うに、現行法制上、教育に関する地方自治の原則が採用され、それが現行教育法制における重要な基本原理の一つをなすものであることからすれば、 文部大臣が地教行法五四条二項によっては地教委にその調査の実施を要求することができないにもかかわらずこれを要求し、地教委をしてその実施に至らせたことは地方自治の原則に反する。 (二)しかしながら、地教委がした実施行為が地方自治の原則に違反する行為として違法となるかどうかは、別個の問題である。 思うに、地教委は、文部大臣の右要求に対し、これに従うべき法律上の義務があるかどうか、また、法律上の義務はないとしても、右要求を一種の協力要請と解し、これに応ずるのを妥当とするかどうかを、独自の立場で判断し、決定する自由を有するのである。 それ故、地教委がみずからの判断と意見に基づき、その有する権限の行使として行った実施行為がそのために実質上違法となるべき理はなく、本件学力調査における調査の実施には、教育における地方自治の原則に反する違法があるとすることはできない。 |

| さて、第11回目は、"三井美唄労組事件"です。 過去問では、平成6年第1問・平成15年第5問・平成16年第4問で出題され、平成10年第20問では前提として問われています。 本判決の原審である札幌高裁は、 被告人らの行為が、憲法28条の保障する労働組合の統制権に基づく行為であるとして、違法性が阻却されると判示しています(検察官の主張によれば、刑法35条の適用とされています。)。 原審が、違法性阻却を認めた根拠は、 被告人らの行為が、労働組合の"統一候補を立てる"という方法による政治活動のために憲法の保障する統制権の行使として行われているからで、 これを分析すると、 ①憲法28条は労働組合に組合員に対する統制権を保障する。 ②この統制権は、労働組合の政治活動についても行使できる。 ③組合員の立候補が組合に対して背信的な場合には、統制権を発動してこれを制限できる。 となります。 この①~③についての検察官による違憲の主張に対してなされたのが本判決です。 ①との関係で『憲法28条が労働組合に統制権を保障すること』との判断が、 ②との関係では『労働組合が政治活動をすることができる』との判断が、 そして、③との関係では『憲法上、立候補の自由が保障されること』及び『勧告・説得の領域を超える行為が統制権の限界を超える』がそれぞれ判断されています。 ※《判旨》の( )のあとのタイトルは、私が要約してつけたもので、判決文にはついておりませんので、その点はご了承ください。m(__)m |
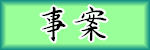
| 被告人ら組合幹部が、独自に立候補する旨の意思を表示した組合員に対して行った行為が、公職選挙法第225条にあたるとして起訴された刑事事件。 |
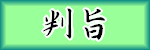
| (1)労働組合の統制権 憲法二八条は、労働者が使用者たる企業者と対等の立場で利益を主張して、その労働条件を適正に維持し改善することができるようにするため、 使用者対被使用者という関係に立つ者の間において、団結権、団体交渉権および団体行動権(いわゆる労働基本権)を保障した。 かかる憲法二八条、及び、これを具体化した労働組合法は、直接には、労働者の使用者に対する労働基本権を保障するものにほかならない。 ただ、労働者が憲法二八条の保障する団結権に基づき労働組合を結成した場合において、その労働組合が正当な団体行動を行うにあたり、 労働組合の統一と一体化を図り、その団結力の強化を期するためには、 その組合員たる個々の労働者の行動についても、組合として、合理的な範囲において、これに規制を加えることが許されなければならない(以下、これを組合の統制権とよぶ。) 。 これは、一般の組織的団体に保障される統制権とは異なり、 労働組合の団結権を確保するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、労働者の団結権保障の一環として、憲法二八条の精神に由来するものということができる。 この意味において、憲法二八条による労働者の団結権保障の効果として、 労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有するものと解すべきである。 (2)労働組合による選挙活動と統制権 労働組合は、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とするものであるが、 現実の政治・経済・社会機構のもとにおいて、労働者がその経済的地位の向上を図るにあたっては、単に対使用者との交渉においてのみこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、 労働組合が右の目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な政治活動や社会活動を行うことを妨げられるものではない。 この見地からいって、本件のような地方議会議員の選挙にあたり、労働組合が、その組合員の居住地域の生活環境の改善その他生活向上を図るうえに役立たしめるため、その利益代表を議会に送り込むための選挙活動をすること、 そして、その一方策として、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することは、組合の活動として許されないわけではなく、また、統一候補以外の組合員であえて立候補しようとするものに対し、組合の所期の目的を達成するため、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することも、それが単に勧告または説得にとどまるかぎり、組合の組合員に対する妥当な範囲の統制権の行使にほかならず、別段、法の禁ずるところとはいえない。 しかし、このことから直らに、組合の勧告または説得に応じないで個人的に立候補した組合員に対して、組合の統制をみだしたものとして、何らかの処分をすることができるかどうかは別個の問題であり、この問題に応えるためには、まず、立候補の自由の意義を考え、さらに、労働組合の組合員に対する統制権と立候補の自由との関係を検討する必要がある。 (3)立候補の自由の意義 自由かつ公正な選挙の実現は、民主主義の基盤をなす選挙制度の目的を達成するための基本的要請である。 この見地から、選挙人は、自由に表明する意思によってその代表者を選ぶことにより、自ら国家(または地方公共団体等)の意思の形成に参与するのであり、誰を選ぶかも、元来、選挙人の自由であるべきであるが、 多数の選挙人の存する選挙においては、これを各選挙人の完全な自由に放任したのでは選挙の目的を達成することが困難であるため、公職選挙法は、自ら代表者になろうとする者が自由な意思で立候補し、選挙人は立候補者の中から自己の希望する代表者を選ぶという立候補制度を採用しているわけである。 したがって、もし、被選挙権を有し、選挙に立候補しようとする者がその立候補について不当に制約を受けるようなことがあれば、そのことは、ひいては、選挙人の自由な意思の表明を阻害することとなり、自由かつ公正な選挙の本旨に反することとならざるを得ない。 この意味において、立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持するうえで、きわめて重要である。 このような見地からいえば、憲法一五条一項には直接規定していないが、被選挙権者、特にその立候補の自由もまた、同条同項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである。 さればこそ、公職選挙法に、選挙人に対すると同様、公職の候補者または候補者となろうとする者に対する選挙に関する自由を妨害する行為を処罰することにしているのである。(同法二二五条一号三号参照)。 (4)労働組合の組合員に対する統制権と立候補の自由との関係 労働組合は、その目的を達成するために必要な政治活動等を行うことができるので、本件の地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進することとし、 統一候補以外の組合員で立候補しようとする組合員に対し、立候補を思いとどまるように勧告または説得することも、その限度においては、組合の政治活動の一環として、許されるところと考えてよい。 また他面において、労働組合が、その団結を維持し、その目的を達成するために、組合員に対し、統制権を有することも、前叙のとおりである。 しかし、労働組合が行使できる組合員に対する統制権には、当然、一定の限界が存するものといわなければならない。 殊に、公職選挙における立候補の自由は、憲法の保障する重要な権利であるから、これに対する制約は、特に慎重でなければならず、組合の団結を維持するための統制権の行使に基づく制約であっても、その必要性と立候補の自由の重要性とを比較衡量して、その許否を決すべきであり、その際、政治活動に対する組合の統制権のもつ前叙のごとき性格と立候補の自由の重要性とを十分考慮する必要がある。 原判決の確定するところによると、本件労働組合員たるXが組合の統一候補の選にもれたことから、独自に立候補する旨の意思を表示したため、被告人ら組合幹部は、Xに対し、組合の方針に従って右選挙の立候補を断念するように再三説得したが、Xは容易にこれに応ぜず、あえて独自の立場で立候補することを明らかにしたので、ついに説得することを諦め、組合の決定に基づいて本件措置に出たというのである。 このような場合には、統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、組合が所期の目的を達成するために、立候補を思いとどまるよう、勧告または説得をすることは、組合としても、当然なし得るところである。 しかし、当該組合員に対し、勧告または、説得の域を超え、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するがごときは、組合の統制権の限界を超えるものとして、違法といわなければならない。 |

| 長きにわたり、お付き合いいただいた"判肢拾弐選"もいよいよ今回で最終回となりました。 皆さんの択一試験の勉強にわずかでもお役に立てていれば幸いです。 思えば、短めの判例から膨大な判例まで様々ありました・・・ とくに印象に残っているのは「旭川学テ事件」。 もう勘弁してくれ~って感じでした。 えっ、感傷に浸ってないでサッさと先へ行けって!? これは失礼しました。 さて、最終回は、"共産党袴田事件"です。 過去問では、平成5年第7問・平成8年第12問・平成15年第9問・平成17年第11問・平成18年第18問で出題され、平成16年第12問では微妙ですが一応問われています。 この判例が、平成の出題で一番の頻出判例でした。 私的にはもう少しメジャーな判例が一番になるかと思っていたので、少々意外な印象がありましたが、皆さんはいかがでしょうか? 原審によれば、日本共産党の機関である党中央委員会と上告人の間には、 「上告人は、党幹部としての地位に在る限り、本件建物を引き続き利用することができるが、その地位を失った場合には、党の要求に応じて、本件建物を明渡さなければならない」旨の契約があったとされています。 それゆえに、党による請求の前提として、"上告人が党幹部の地位にないこと"が必要となり、さらにその前提として"党による除名処分が有効であること"が問題となりました。 これとの関係で、本判決は、そもそも裁判所が「政党による党員の除名処分の有効性」を審査することができるのか?を明らかにしました。 |
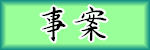
| 日本共産党による上告人に対する所有権に基づく家屋明渡等請求事件。 |
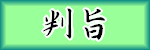
| 政党は、政治上の信条、意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であって、内部的には、通常、自律的規範を有し、その成員である党員に対して政治的忠誠を要求したり、一定の統制を施すなどの自治権能を有するものであり、国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効な媒体であって、議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在であるということができる。 したがって、 (憲法は、) 各人に対して、政党を結成し、又は政党に加入し、若しくはそれから脱退する自由を保障するとともに、政党に対しては、高度の自主制と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない。 他方、右のような政党の性質、目的からすると、自由な意思によって政党を結成し、あるいはそれに加入した以上、党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために、自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあることもまた当然である。 右のような政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、 したがって、 政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないというべきであり、 他方、右処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、右処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし、右規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、その審理も右の点に限られるものといわなければならない。 本件記録によれば、被上告人は前記説示に係る政党に当たるということができ、本訴請求は、要するに、被上告人と上告人との間で、上告人が党幹部としての地位を有することを前提として、その任務の遂行を保障する目的で上告人に党施設としての本件建物を使用収益させることを内容とする契約が締結されたが、上告人が被上告人から除名されたことを理由として、本件建物の明渡及び賃料相当損害金の支払を求めるものであるところ、右請求が司法審査の対象になることはいうまでもないが、他方、右請求の原因としての除名処分は、本来、政党の内部規律の問題としてその自治的措置に委ねられるべきものであるから,その当否については、適正な手続を履践したか否かの観点から審理判断されなければならない。 そして、所論の点に関する原審の事実認定によれば、被上告人は、自律的規範として党規約を有し、本件除名処分は右規約に則ってされたものということができ、右規約が公序良俗に反するなどの特段の事情のあることについて主張立証もない本件においては、その手続には何らの違法もないというべきであるから、右除名処分は有効であるといわなければならない。 |